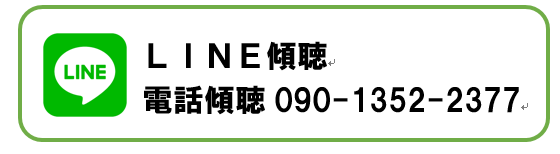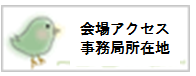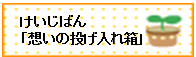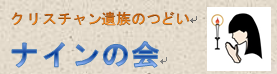自死遺族の心理を描く新聞小説「風は西から」
3か月くらい前から、家人が契約した中国新聞セレクトを読むようになりました。
連載小説の「風は西から」(村上由佳:作)に何気なく目を通し始めたのは2か月ほど前でしょうか。
恋人の男性が職場の長時間労働やパワハラによって追いつめられ、自死してしまう。
遺された彼女、彼の両親と共に会社と戦っていく(のであろう)のがこれからのストーリーです。
毎朝、この小説に、半分恐る恐る、半分急かされるように目を通します。
自死遺族の気持ちを軽々しく語るような文章があったら傷つく、、、
あまりに自分の身に迫る話だと一日気分が落ち込む、、、そんな不安もあり。
確かに、小説を読んで、フラッシュバックしてしまい、「仕事前に読まなかったらよかった」と思ったことは何度もありましたが、
自死に向かう程追い詰められていく彼の姿の描き方も
すぐ近くにいながら、ちょっとしたすれ違いで、目前で彼を救えなかった彼女の痛切な自責と後悔の想いも、
私の目には、克明に(ある意味容赦なく)、また、余計な虚飾がなく書かれているように思います。
私が一番心に残っているのは
彼のために、会社と戦う決意をした彼女(千秋)の
「失うものなんか何もなかった。いちばん大事なものは、すでに失ってしまったのだから。」という一節です。
また、その後、彼の両親と彼女が、彼の死の直前の行動について、色々な推測を重ねながら
「意味がないとわかっていても、時間の巻き戻しを繰り返す」(表現は違っているかもしれない)
この言葉も、自分自身に重ね合わせることが多いのです。
先日、中国新聞の取材を受けたときに、
「村山先生は、とてもていねいに取材をされたのではないですか?」と聞いたところ、
その通りであると、また、自死遺族からこのような感想があることを先生にも伝えます、と言われました。
数日前から、彼を死においやった会社の幹部との戦いが始まっています。
ここは、フィクションとして(現実にはそんなわけにいかないかもしれないが)ぜひ勝利の結末にしてほしい。
自死に至る前も、自死遺族になった後も、残酷な現実に心を打ち砕かれ続けている遺族のためにも。