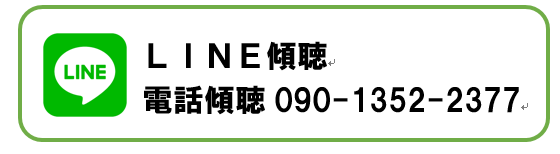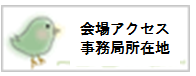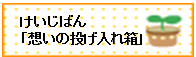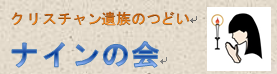「突然死」と「余命を知った上での死」
「あなたは「余命を宣告された上での最期と突然死による最期を選べるとしたらどちらを選ぶ?」
という問いかけがカウンセリング教室の死生観に関する講義の中であった、と聞きました。
私は、迷わず「余命を知った上での最期」を選びました。
余命がわかっていれば、人生でやり残したことをして、
残る人に別れを告げ、死後に残すべきものを整理し、
愛する人との残りの日々を悔いなく過ごせると思ったからです。
これは、裏返すと、突然の死によって遺された者の想い。
「もっとこんなことをしてあげたかった」「いろいろな話を聞いておきたかった、話したかった」
そんな悔いと自責感からくるもの。
なんの予告もなく死んでしまった人間の遺したものを手に取って整理する辛さからくるもの。
でも、「余命宣告」は、最期の日を決めるものではない。
ここ数年、親族の死が続きました。ほとんどは高齢か、持病の末の死でしたが、
どんな重病の床にあっても、本人も,周りの者も、最期の日への覚悟より
「もう1日生きよう」「まだがんばれる」と信じ続けていたように思います。
私の父は、死の半年前から急に体のいろいろな器官が悪くなり、
最期は腎不全が見つかり、入院後1か月で亡くなりました。
尿がほとんど出なくなり、意識が混濁し、余命を言われましたが
「いよいよ」と覚悟を決めた直後、一転、きれいな尿が出るようになり、体調も回復。
「よくなるかも」と希望を持って長期療養型病院への転院の手続きをしている矢先に
容体が急変して亡くなりました。
90代で亡くなった義理の祖母は、こん睡状態に陥り、今日明日、と言われた中で目を開け、
水さしを差し出されて、「こんな味のないものは飲みとうない、ワインなら飲みたくなるが」と言い、
枕元の人間が「こんな冗談が言えるなら大丈夫」と笑った次の日、亡くなりました。
その日を静かに迎える、なんてできるだろうか?
人は最後の灯が消えるまで、
本人の意識がなくなっても、体は命の火を燃やそうとするのではないでしょうか。
それほどに、人間の本能の中に埋め込まれている「生きたい」とする力は、本来、強い。
父をずっと献身的に看病していた姉は、死後、「もっとあの時ああしていれば」と悔いていました。
私から見ると、これ以上なく尽くしたと見える姉でした。
どんな最期であっても、遺された者は辛く、自分を責める。
死とはそういうものです。