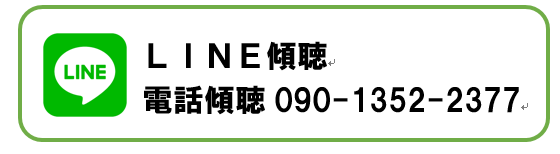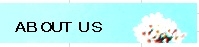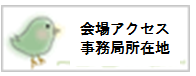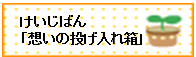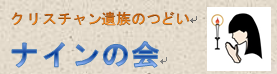答えが見つからない苦しさ
心因性の難病で外出ができない1人ぐらしのAさん。
私も週に1回話に行きますが、日常的な話し相手は週に3回の訪問看護士さん。
それが、1回あたりの訪問時間が3月からほぼ一方的に、1時間半から30分に短縮されてしまったそうです。
「自立を促すため」というのがその理由だそうです。、
地域包括支援センターの「外出支援」で、少しずつでも自力で外出できるように訓練はしていますが
パニック障害、広場恐怖症が重いAさんにとって
「自立しようと‘意志を持ってがんばれば’外出できる」とは簡単にいかない。
「パニック障害」については
http://www.hoshi.tv/cat2/post_4.html
Aさんの症状も生活状況もよく知っているプロが、いきなりの方針転換、なぜでしょうか。
しかも、Aさんの「枠」(本人の言葉による)は1時間半のままで減っていないのに、
看護士が個人的な判断で「その方がいい」と決めた、ということなのです。
Aさんは在宅医療も利用していますが、
月に1回往診する診療内科クリニックの医師に対しても、訪問看護士に対しても、
不信感と不満が噴出します。
それは
「なぜ質問に答えてくれないのか」「なぜ訴えを聞き流すのか」「なぜ一方的に決めるのか」
その答えをくれない、ということです。
そんな不満があるなら、別の機関に変えたら、とは、自分に十分な選択肢がある人間の論理。
「自分から何かを新しく変える」ことに伴う不安の大きさも、Aさんにとって大きなストレスなのです。
医師も看護士も、それなりの方針や考え方があって「そうしている」のかもしれない。
「客観的な目利き」による判断があるのかもしれない。
でもAさんが納得できていないから、私に訴えてこられる。
話を聞いて私がもどかしいのは
他人の私は、本人がいない場で、その「客観的な目利き」について聞くすべがない、ということです。
Aさんの聞き違いや思い違いがあったとしても、それさえわからない。
Aさんの話から覚える‘憤り’さえ、それが正しいのかさえ判断できない。
「自分も、外に出て色々な人と話ができる体になりたいと思っている。
でも、いまは無理なんです。せめてそれができるまで、もう少し続けてもらえないのか」
Aさんの一番の不安は「会話相手がいない」圧倒的に長い時間が、自分を「話ができない人間」にしてしまうのでは、ということ。
「勇気をもって、『自分の持ち枠は1時間半あるのだから、1時間半来てください』と看護士さんにお願いすることはできませんか?」と
絞り出すように言った私の言葉に、Aさんの表情が脳裏から離れません。