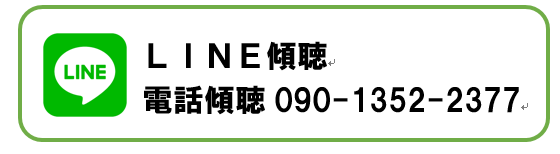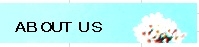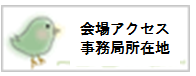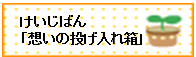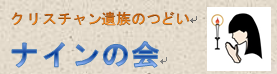ジョゼの幸せ
こころのともしび」のアイドル猫(笑)、ジョゼ。現在17歳です。(人間なら80歳)
7歳のときに糖尿病が見つかり、以降10年間、朝晩インスリン注射が欠かせません。
インスリンによる治療は投与量の加減が難しく、体調の変化によっては、血糖値が極端に下がる「低血糖発作」を起こし、発見が遅いとそのまま死に至ります。また、人間のように自宅で血糖値が測れないので、『今の血糖値を見つつ、その都度注射量を調節する』ことができません。
ジョゼも何度も発作を起こし、死の直前までいったことも何度もあります。
夜中に「夜間動物救急病院」にタクシーを走らせたことも何度もあります。
適正な血糖値は「100~200」。その数値を保つために獣医師も私たち飼い主もインスリン投与の量を神経質なほど調整してきました。
が、このたび、獣医師は、「ジョゼの身体の安全を最優先するために、多少高血糖になることに目をつぶっても、インスリン注射の量を最低限にしましょう。」と判断しました。
考えてみると、私たちは何を目標に、何を一番大事にしてきたのか。
ジョゼ自身より、「適正な血糖値」という『数字目標』ではなかったのか、、、
獣医師の言葉にはっとさせられました。
一番大事なのはジョゼ自身が安全に気持ちよく過ごせることなのに、、、
人間の「かくあるべき」という考えに固執していたんだよね。
いまは獣医師の言葉通り、最低限のインスリン投与に抑えています。
高齢ですから、いつまでも一緒にはいられないこともわかっています。
他の病気もちらついています。
糖尿病が原因で体にいろいろな衰えも見え隠れしています。
気を付けていても低血糖発作で突然逝ってしまうことも覚悟の上です。
でもね、天命をまっとうするまで一緒にいようね、「ともしび」のみなさんにかわいがってもらいながら楽しく、暮らしていこうね、ジョゼ。
2023年10月26日 18:35