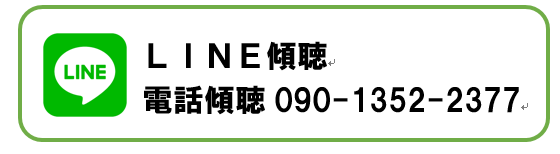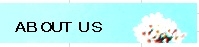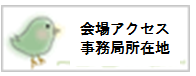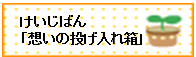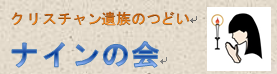先週は15日の広島テレビさんが自宅に取材で来られた日から始まった。
17日から「自死遺族の想いを伝えるパネル展」が始まり、
現場のお手伝いをしたり、取材のために待機していたりで、昼は事務局と会場を行ったり来たり。
夜は、事務局でシンポジウムで配布する資料を印刷し、名簿を整理し、スタッフの役割表を作る。
未成年殺人事件の報道や参議院選挙前で、取材はないかな、思っていた広島テレビさんが
19日には約束通り会場に取材で来てくれました。
19日の18時25分から地方ニュースの枠内でとても丁寧に5分の番組に仕上げてくれていて、感動しつつ、「え、これ、自分(@_@)」となんだか驚いたな~。
一緒に見ていた 基調講演講師の田中幸子さんも、「いいね、すごく誠意があるし、まじめにとりあげてくれている。こういうものは、記者の良心がでるのよ」と絶賛。
その後、田中さんや他の関係者と「前夜祭」(?)
20日はいよいよ、本番。講演の内容もそうですが、裏方の準備や受付、会場の管理など、
事務的なことで粗相があっても、来てくれた方に失礼と、緊張します。
そんなこんなで、あっという間に本番。始まってみたらあっという間でした。
前日のテレビの効果もあり、シンポジウムにもパネル展にも多くの方が来てくださいました。
打ち上げ会もにぎやかに終了。11時ごろ帰宅。
日曜日の朝は、支援してくださった広島教会にお礼を兼ねて礼拝に行き、
その後、誘われていた「うつと躁うつ病を考えるフォーラム」(NHK厚生文化財団主催)を見に行く。
夕方、東京から来てくれた娘と彼氏を広島で見送る。
怒涛のような1週間でした。
普通なら新聞やテレビに一生出ないような一般市民。とてもよい経験をしました。
準備を初めてから3か月間、
多くの人との新たな出会い、応援、再会もあり、感謝、感謝、感謝です。
でも、改めて思ったな。
「少数でも、ゆっくり向き合うのがが自分らしいな」って。
パネル展で娘の写真をずっと眺めている方がいたので声をかけたら、その方も心に辛いものをもっている方で、「声をかけてくれてありがとう、ありがとう」と涙を流されました。私も泣きました。(写真の後ろ姿は記事とは別人です)
九州から来られていた方にあいさつをしたら、「いつもブログを見ていますよ!」と言っていただきました。
時々、というか結構ひんぱんに、自分が考えていること、やろうとしていることが、とてつもない「空振り」なのでは、と思うことがある。
でも、こういう出会いがあると、よかったな~(#^.^#) って強く思って元気が出る。
そういう出会いを地道に続けていきたい。
2013年07月22日 20:21