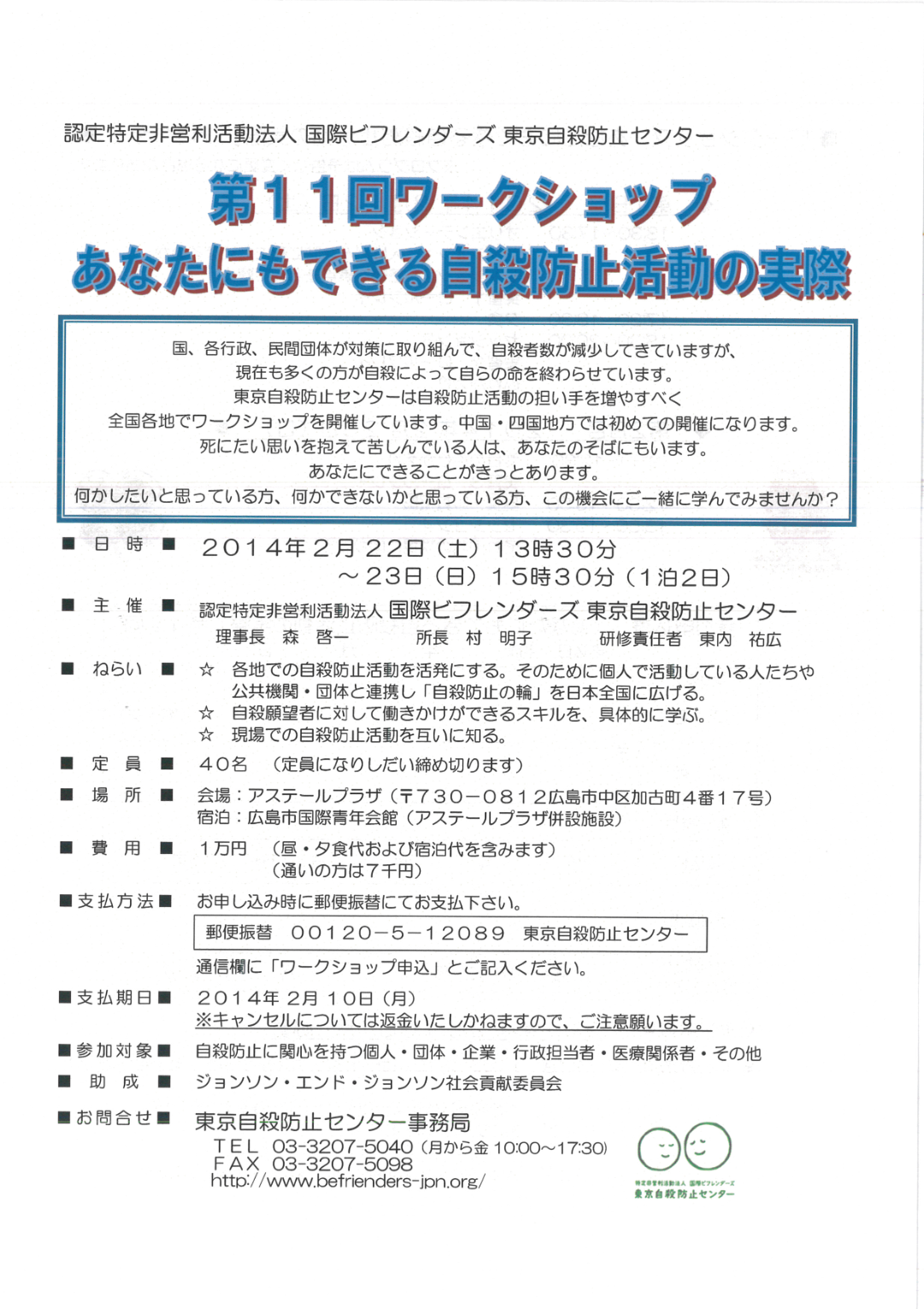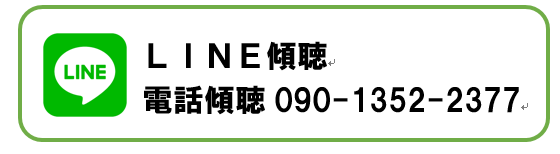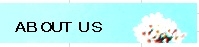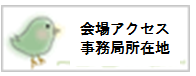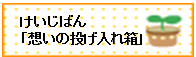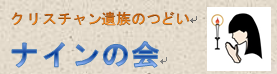先週22日、23日に広島では初めての「東京自殺防止センター ワークショップ」で勉強しました。
2日の日程のほとんどの時間がグループに分かれた「電話相談のロールプレイ」実習に費やされました。
7人程度のグループに1人ずつ指導役のリーダーがつき、
callerと言われる、電話をかけてくる人の役、befrienderと言われる電話相談員の役を交互に実習します。
1日目は指導リーダーがcaller役をし、2日目はグループメンバーがcaller役もしました。
他の人はオブザーバーで、ロールプレイについての感想や評価をする役です。
東京自殺防止センターに実際に寄せられる相談を下敷きにしているため、実習で出される
callerの相談が切迫した、現実感のある内容でした。
それだけに、befrienderも時々行き詰ったり、答えに窮してしまったり、
また、callerを演じる人が、感情移入のあまり、感極まってしまったりと
息詰まる実習で、とても頭が疲れてしまいましたが、中身の深い深い勉強になりました。
東京自殺防止センターをはじめ、全国にある自殺防止センターの電話相談では
callerに対して、「死の意思があるか」の確認をするのがルールです。
つまり、「あなたに『死にたい』気持ちがあるか」を電話口で問う。
はじめは戸惑いました。
明らかに自死したい、という気持ちがある人ばかりでないのでは、
そんな人に「死にたいのか」と問うたら、かえって潜在意識を掘り起して危険なのでは、とも思いました。
でも、実習をしてみて、この「究極」ともいえる、“辛さ”を吐き出せることの大きさを知りました。
普段、身の回りの人に対しては、悩みや愚痴は言うかもしれなくても
「死にたくなるほどつらい」という言葉を口に出すことはできない。
それを「言っていいんだ」と思わせてくれる。
心の中によどんでいる澱を吐き出して、素直な、サラサラとして心になれる。
実習するまでは気づかないものでした。
実習が終わったあと、一緒に研修に参加した家人に
自分も「死にたいという気持ちを抱えている」と、素直に打ち明けることができました。
そして、そのことで、「言えずに言えないままだった」こと、
かさぶたのように心の中にこびりついていたものが解放されたように思いました。
東京防止センターは
「国際ビフレンターズ憲章」
にのっとって活動をしています。
ビフレンターズ=be-frienders」死にたいほどつらい人の『友』として『心』に寄り添う人
辛い人を、崖から落ちておぼれそうな危機にある人に例えるなら、
自分の安全も確保せずに水に飛び込んで一緒におぼれるのではなく、
自分はおぼれないように命綱をつけ、足場を確保したうえで、おぼれる人に手を伸ばす人です。
いままで、「同調してこそ心がわかりあえるのでは」とどこかで思っていた自分を恥ずかしく思いました。
2014年02月25日 19:52