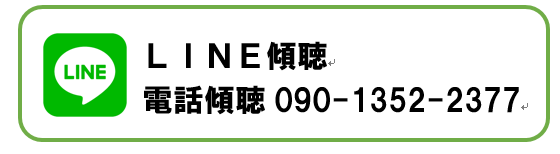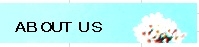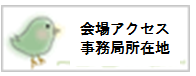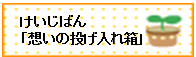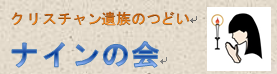神様は1人1人に天使を遣わしてくれるはずなのに
子どものときに、親から愛を与えられず、
「お前なんかいない方がよかった」と言われてずっと、自己否定の中で生きてきた。
他人とかかわりたい、つながりがほしい、と願うあまり
誰に対しても、自分の想いをぶつけることができず、相手の心の中ばかり気になって
一生懸命相手の心を理解しようと努力するあまり、他人のネガティブ思考を自分の中に過度に取りこんでしまうために、
それが原因で、身体に激しい痛みが生じるストレス性の身体障害を持っている。
働くことも、ボランティアをすることも、友人を作るために交流の場に出ることも、
それがゆえに、医者から禁止されている。
いまは、障碍者年金と生活保護で生計をたてながら、投薬治療で健康を維持をする生活。
平均寿命の半分しかまだ人生を歩んでいないのに、「自分はもうこれでいい」と言われる。
「それでも、あなたのような方に会えて、お話ができてよかった」と言われる。
神様、私はこの間、教会で、
神様は、私たち1人1人に、天使を遣わせてくださっていて、
苦しいときや危険なときは、神様がその天使を通じて、私たちを守り導いてくださっている、
と聞きました。
「小さな者が1人でも軽んじられないように」御国から御顔を向けてくださっていると聞きました。
では、神様、その方のもとには、天使を遣わすのをお忘れになったのですか。
その方に遣わした天使は、あなた様にこのような小さき者のことを伝えていないのですか。
どうぞ、忘れないでください。もう一度、この人に御顔を向けてください。
私は祈ることしかできない。