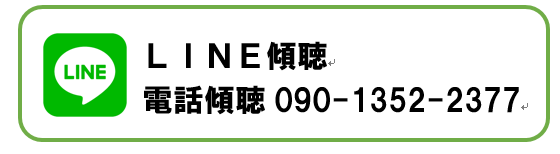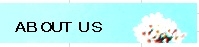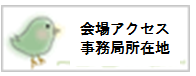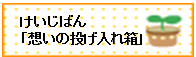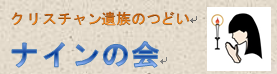肩を抱き、手を握ること
先週末の「うつ症状のある方、またはその家族の会」には、初めて、当事者と支援する家族が一緒に参加がありました。
しかも、2組の方が。
当事者と家族が同席、というのはお互いに遠慮しあってうまく胸の内を語れないのでは、
2つの家族が牽制してしまわないか、と始まる前は心配したのですが
実際に語り始めてみると、
支援家族同志は当事者ががんばっていることを当人の前で語り合い、
隣り合った当事者同士は、肩に手を置き、背中を抱いて、
自分がとてもつらいのに
「よくがんばってるね、えらいね。。。」と声をかけあっていました。
考えてみると、一対一で当事者と支援する家族が向き合っているとき、
支援家族は、愚痴やストレスも口にできないけど、
面と向かって「ほめてあげる」こともできないのかも。
同志がいると、1人ではできないことが自然とできるようになる。
うつ当事者と家族の分かち合い、
こんな形で続くといいな、と思いました。
2014年05月20日 16:56