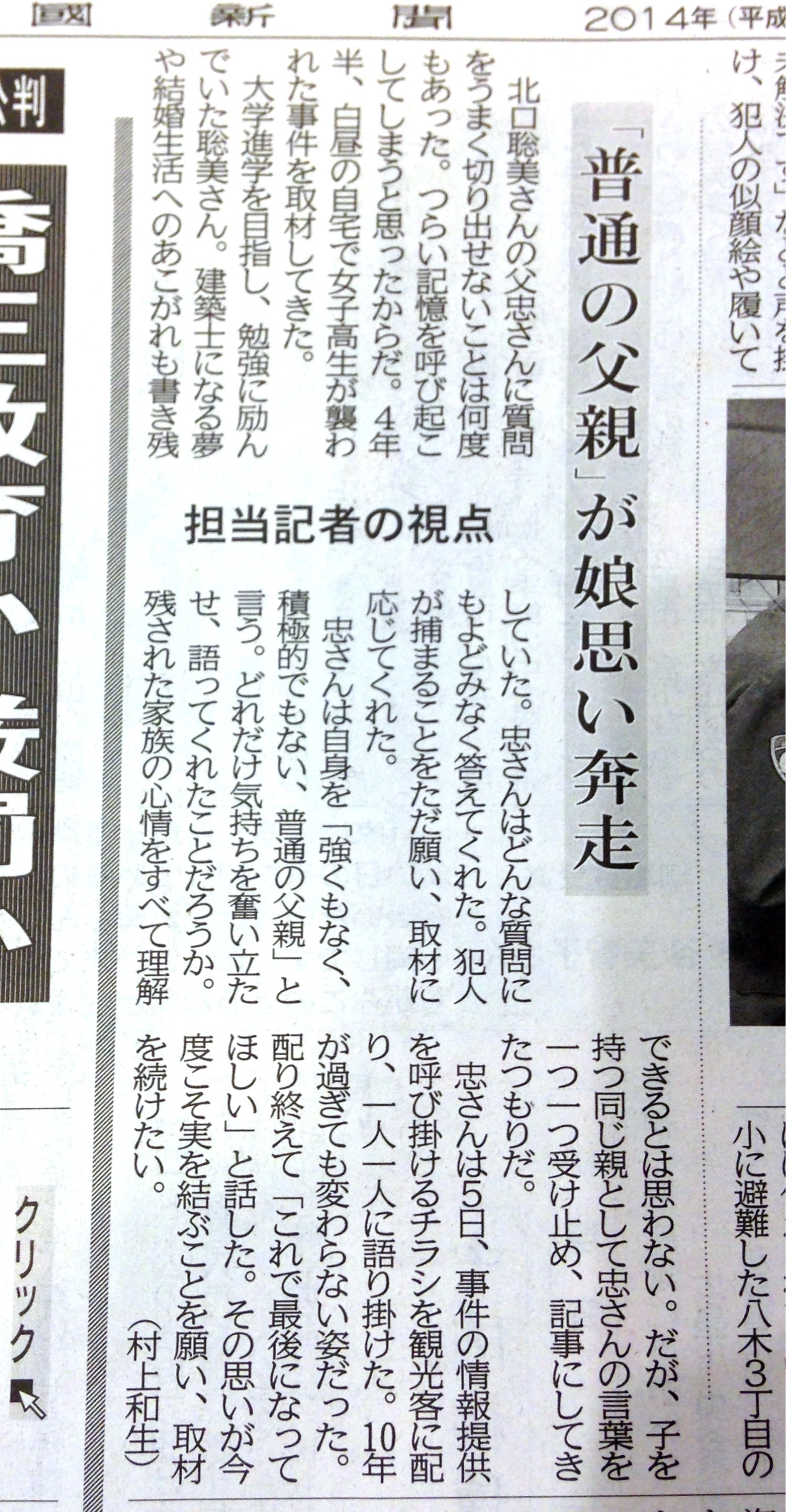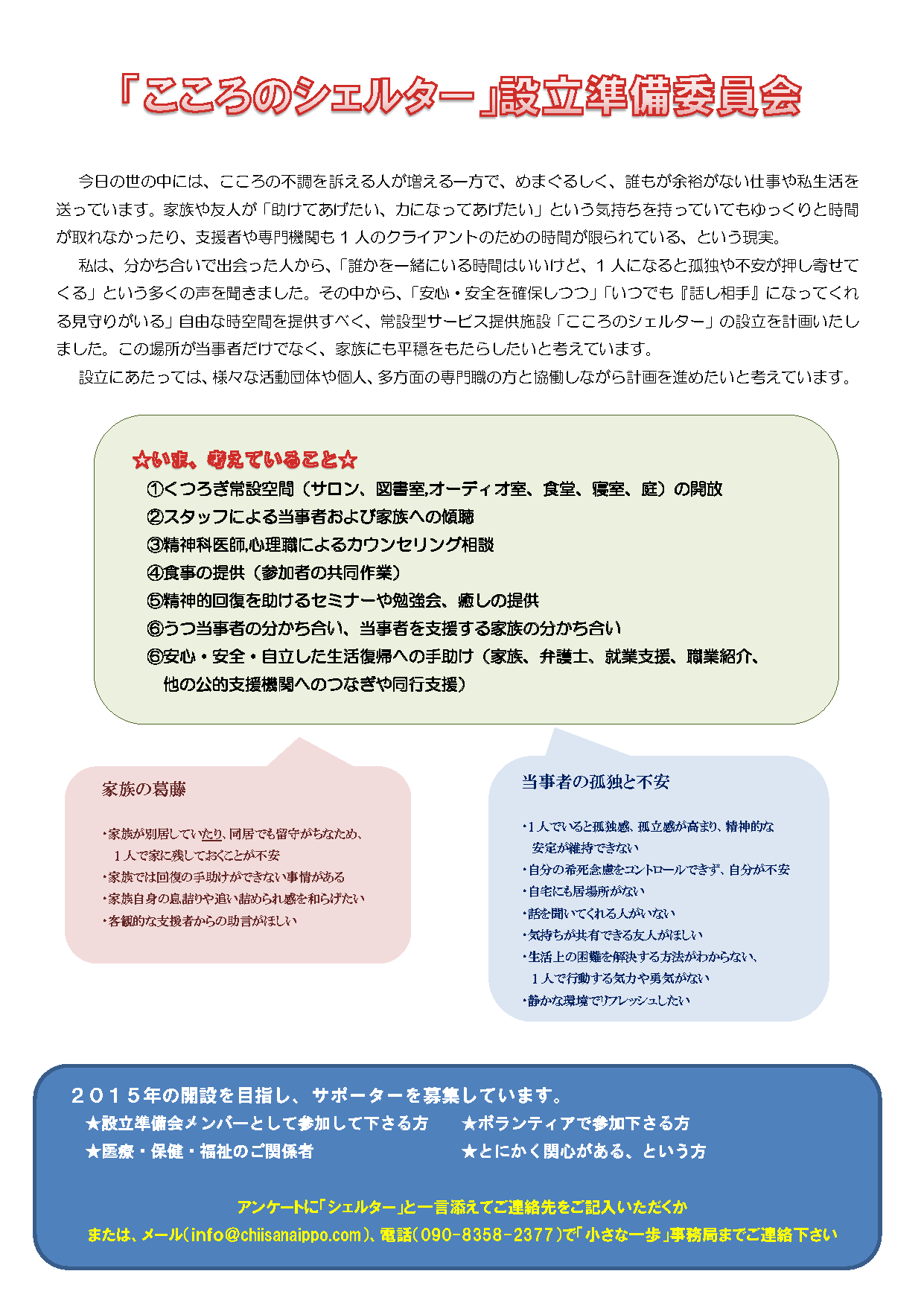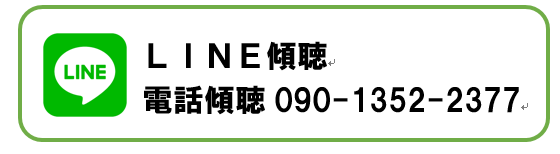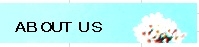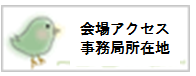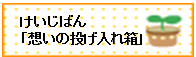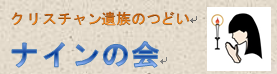命ははかなく、でも力強い

小さな体にたくさんのチューブにつながれ、目もうつろで焦点が定まらず、
抱き上げても体がぐったりしている。
病院の獣医先生の説明では、「この病気は食べないとどんどん衰弱して急速に悪化するので
なんとか食べてもらいたいと看護師がいろいろするのだが、全く食べたがらない。
胃に直接チューブを入れて栄養を入れるかどうか、考えている」とのこと。
「最後まであきらめずに、できる治療は続けます」との言葉から、逆に生存の希望の低さを感じた。
つい1週間前まで元気に跳ね回っていた仔の、急な命の危機に、つい娘のことがフラッシュバックする。
近づいて抱き上げるくと、弱々しい声で鳴き、顔を寄せる。
「もしかして」と、病院食ではなく、ペットショップで、とろみスープを買い、
指に少しずつつけては、歯や舌の周りにすりつけてみると、その感じがいやで本能的にべろべろとする。
根気強くそれを続けているうちに、少しずつ胃に入っていったようだ。
看護師さんにそのことを伝えると、見舞いに行けない間もスポイトで少しずつ与えてくれた。
見舞いに行くたびに、半ば無理やりに口の周りに流動食をすりつけていたら
昨日になって、少しずつ血液検査の値がよい方向に向かい、
目に力が出てきた。今朝には、前足で立ち上がるところまで回復した。
病院のスタッフに「おかあさんが、来てごはんをあげて声をかけてあげると全然違いますよ!」
と声をかけられた。
その間、娘に
「天国がさびしいか退屈か知らんが、まだジョゼは若いんだから、呼ぶのは早いよ!
もう少し待ちなさい」と言い聞かせた。
願いは通じたようだ。
5kgの小さな体でも、「生きよう」と懸命に闘う力には変わりない。
全ての愛する者には、命の限り生きてほしい、と改めて思った。