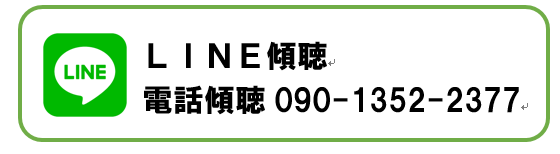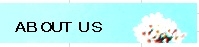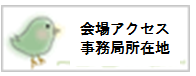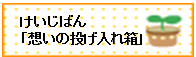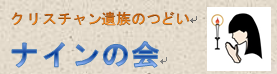21日は2度目の命日、22日は5月5日に亡くなった父と一緒に教会で慰霊式をしました。
慰霊式では、家族が元気だった、20余年にわたる集合写真をスライドにして、集まった家族で見ました。
「ああ、この中で2人がもういないんだね」。。姉がつぶやいた。
自死で子どもを亡くすというのは、グリーフサポートの専門書にも「最も強い悲嘆」とある。
確かに、2年たった今でも、哀しみがいつも隣り合わせにある。
いまも、娘が最後に住んでいた場所には行く勇気がわかない。
同じ方面に用事で行かなくてはいけないとわかると
近づくにつれて、鼓動が激しくなり、口の中が乾き、ハンドルをぎゅっと握ってしまい、
いやだいやだ、と頭の中で声がこだまする。
娘のことを思い出させるシーンや物事に会うと、泣かないようにしっかりと足を踏みしめる自分がいる。
では、それ以外の喪失はこれに比べて軽いのでしょうか。比較があるのでしょうか。
父は生涯をまっとうして87歳まで生き、長患いをせず逝ったけど、
そういう理屈ではなく、別れは悲しい。命がなくなることは、単純に悲しい。
命日の前日に、広島女学院大学にシンポジウムの広報のご協力にお伺いし、
長尾学長に快くうけていただいた後に、
昼の礼拝が始まるところだったので参加しました。
23日の沖縄戦終結の日を前に、沖縄への慰霊式が行われていました。
民族楽器の三線の伴奏で歌う「いつくしみ深い」。娘の臨終の枕元で歌った同じ讃美歌です。
これも何かの偶然の出会いでしょうか。
私たちは、自死遺族の悲嘆が、経験したことのない人に理解されないと訴えるが
では、
沖縄の遺族、広島や長崎原爆の遺族、神戸や東日本の震災や災害の遺族、事故死の遺族。。。。。
私たちは、お気の毒だ、悲劇だと思うが
遺族の方々の気持ちはとてもではないが、理解しきれていないと思う。
自死遺族の気持ちが、当事者以外の人間に理解しにくいように。
「わかる」ことは、できないのです。
ただ、「わからないから無理」とは言わない。
「ごめん、正直、きっと同じようにわかることはできない私だけど、よりそっていていいかな?」
これくらいしか、役に立たない、と思う。
自死遺族も含め、お互いがそうであってほしいと思う。
2013年06月24日 17:54